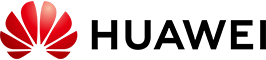MWC 2016
早春を感じさせるバルセロナで今年も『Mobile World Congress(MWC) 2016』が開催された。来場者は10万人の大台を超え、会場では各社がこぞって最新端末や次世代の無線技術を披露。スマートフォン市場減速にも関わらず、“モバイル業界最大のイベント”にふさわしい内容となった。

ホール1のファーウェイ・ブースは「オープン」がキーワード。例年は招待者のみ入場できるが、今年は最終日に一般公開した
個性豊かな各社の端末
今年のMWCは2月22日から4日間。事前登録の時点で昨年を上まわる9 万5,000人といわれていたが、会場のフィラ・グラン・ヴィアには世界204か国から過去最高となる10万1,000人の参加者が押し寄せた。直前にバルセロナ市交通当局である都市輸送公社がスト決行を発表、初日から3日間地下鉄とバスの間引き運転が行われた。それでも大きな事件もなく、参加者は郊外にあるフィラに足を運んだ。
今年は10万平方メートルの展示スペースに2,200社がブースを構えた。注目は、やはり端末メーカーがひしめくホール3だろう。MWCでは例年前日に端末メーカー数社が新製品を発表するが、今年はサムスン、ファーウェイ、LG、ZTEなどが市内で発表会を開催したほか、ソニー、レノボなども会期中に最新機種を発表した。
似たり寄ったりと言われるAndroidスマートフォンだが、各社の発表した製品からは、オリジナリティを出そうという試みが感じられた。たとえばLGは、フラッグシップの『LG G5』を発表したが、その特長は“モジュラー・スマートフォン”だ。モジュラー式はGoogleの『Project Ara(プロジェクト・アラ)』などいくつかの取り組みが進んでおり、ニッチではあるものの動向が注目される分野だ。『G5』の場合、バッテリー部分を外してカメラ、ハイレゾ対応Hi-Fi DAC(Digital-to-AnalogConverter:デジタル・アナログ変換機)を装着できる。
ソニーは最新のスマートフォン『Xperia X』『Xperia X Performance』など3機種を発表、スペックを追求するのではなく、デザインとソフトウェアによる使いやすさに軸足を移した。同時に発表したスマート・イヤフォン『Xperia Ear』など周辺機器にも『Xperia』ブランドを拡大し、ユーザーの環境に溶け込むデジタル・ライフ観を示した。このほか、サムスンは今年も最新のフラッグシップ『Galaxy S7』『Galaxy S7 edge』を、ZTEも『BladeV7』を発表した。
そんな中、シェア3位のファーウェイはスマートフォンでもスマートウォッチでもなく、2-in-1型のWindows 10タブレット『MateBook』を発表した。画面は12インチながら、サイズ278.8×194.1×6.9ミリメートル、重さ640グラムとコンパクト。プレゼンのページ送りやポインターに使えるスタイラス・ペンも付属し、「Business3.0」の実現を謳っている。マイクロソフトの『Surface Pro』対抗と位置付けられるビジネス向けの仕様だが、電源ボタンと指紋認証センサーを側面に配するなど、既存のPCメーカーとは異なるアプローチで、新しい端末を求めるビジネスユーザーに訴求する。「現在のPCは、コンシューマーのニーズを満たしていない」とコンシューマー事業CEOの余承東(リチャード・ユー)氏は述べた。
このようにスマートフォンで知られるファーウェイがPC市場に参入する一方、PCメーカーのHPはWindows 10スマートフォン『HP Elite x3』を発表するなど、“モバイル”の境界線があいまいになったことを感じさせた。端末側では中国市場を中心に展開するシャオミが会期中、欧州で初めて製品発表会を行った点も興味深い。

開幕前日の発表会で、2-in-1のWindows 10タブレット『MateBook』を発表するファーウェイの余承東氏
Facebookも熱い期待を寄せるVR
IDCの推計によると、世界スマートフォン市場は2015年に成長率9.8%と初めて1桁成長へとダウンした。各社は成熟市場で生き残りをかけており、昨年まではその戦略がスマートウォッチ、ウェアラブルに集中していた。だが、今年は上記のように幅が広がった印象がある。そして、デバイス側ではもうひとつ、VR(Virtual Reality:仮想現実)への期待をあちこちで感じることができた。
サムスンの『Galaxy S7/S7 edge』の発表会でも、影の主役はVRだったといってよいだろう。同社の『Gear VR』はFacebook傘下のオキュラス(Oculus)と共同開発した製品で、発表会ではFacebookの共同創業者兼CEOマーク・ザッカーバーグ(Mark Zuckerberg)氏がサプライズ出演し、「ソーシャル・メディアのプラットフォーム」としてのVRの重要性をアピールした。なお、会場ではプレスに1人1台『Gear VR』が貸し出され、司会者の指示のもと全員が同ヘッドセットを装着している間、ザッカーバーグ氏が悠々と会場の通路を通る姿が自身のFacebookページに掲載された。この写真は、「これがわれわれの将来なのか?」と物議を醸し、ソーシャル・メディアなどで瞬時に広まった。
ザッカーバーグ氏は初日のMWCのメイン・イベントでも基調講演を行い(後述)、テキスト、写真、動画、と共有のための媒体が進化してきた歴史を振り返った。現在、Facebook上で360度動画を閲覧する人は1日100万人以上といい、VRの時代が近づきつつあることを予言した。一方で、このようなリッチなコンテンツの潜在需要を満たすためには「高速な5Gネットワークが必要」と述べ、「VRは5Gのキラーアプリになると期待している」とコメントした。
このほか、会場では『HTC Vive』の価格を発表しVR一色だったHTCをはじめ、サムスンは『Gear VR』によるジェットコースター体験、SKテレコムは海中体験、地元のカタルニア地方観光局は観光地体験など、あちこちでVR体験コーナーが設置され、連日長蛇の列ができていた。


クアルコム(上)やSKテレコム(下)のブースにもVRコーナーが設けられ、来場者の注目を集めた

FacebookのCEO、マーク・ザッカーバーグ氏がFacebookに投稿したサムスンの発表会でのワンシーン。SNSで瞬く間に広まった(写真:Facebook/Mark Zuckerberg)
5Gへ―― 進化の道程
ネットワーク側では、昨年に続き5Gがキーワードとなった。2015年よりMWCで5G通信のデモを行っているエリクソンは、今年もNTTドコモと行っている実験を披露した。実験は現在フェーズ2となり、昨年と同様に15GHz帯を利用し、Massive MIMOアンテナ技術などの利用により帯域幅は800MHzに。1台は移動、1台は固定と2台の端末を用い、ビーム追従を行うことで合計速度は昨年の約5倍の25Gbps程度に達していた。
アルカテル・ルーセントの買収が完了し、歴史あるベル研究所を手に入れたノキアも、15GHz帯を利用した5G通信を披露した。ノキアは単に速度を見せるのではなく、用途としてVRをデモ。インストラクターと生徒がそれぞれVRを装着してコラボレーションする、という利用例を見せた。速度は5Gbps程度だったが、フルでシステムを動かすと倍の10Gbps程度に達するとのことだった。
ファーウェイは上海にあるラボで行っている5G通信の実験を展示し、画面では20Gbps以上のスループットを達成していた。一方、同社は4Gから5Gへの進化過程における現実的な速度対策、遅延対策として、昨年に引き続き「4.5G」を打ち出している。これは2015年10月に3GPPで「LTE-Advanced Pro」としてRelease 13に入ることが決定した技術で、ファーウェイのブースでは、Massiveキャリアアグリゲーション、MassiveMIMO、256QAMにより1Gbps以上の速度を実現すると解説していた。これにより、VR、HD Voice、HD Videoなど同社が「Experience 4.0」と呼ぶ体験が可能になるという。すでに2015年末にノルウェーのテリアソネラとライブ・ネットワークにおける4.5Gのデモに成功しており、今年はローンチ・ラッシュになるとファーウェイは見込む。

ファーウェイは4.5Gを前面に打ち出す
LTEを活用するIoT規格「NB-IoT」
ファーウェイが4.5Gをプッシュする理由は、速度や低遅延だけではない。NB-IoTがある。NB-IoTは10年以上のバッテリー持続時間、カバレッジ、低い総所有コスト(TCO)などを特長とするIoT通信技術だ。
初日のメイン・プログラムのステージに立ったファーウェイの輪番CEO、郭平(グォ・ピン)氏は、「5Gを待たず、すぐに動き始めなければならない」と呼びかけた。差し迫っているのはIoTのニーズだ。ファーウェイは「2025年には1,000億の人とモノがネットワークにつながるが、そのうち人の接続は1割に過ぎない」という予測を立てており、IoT時代に向けて「4.5Gがまずはデジタル革命の土台の技術になる」と郭氏は強調した(巻頭メッセージ参照)。ファーウェイはボーダフォンなどとNB-IoTを推進するNB-IoTフォーラムも立ち上げており、会期中に同フォーラム初のサミットを開催している。
IoT用の通信としては、同じく3GPPで作業が進んでいるeMTCをエリクソンがデモしていた。LTE-MはNB-IoTより高速な通信が可能であるなど特長が異なるため、用途も異なるとされる。
ファーウェイのビジネス&ネットワーク・コンサルティング部門プレジデント、ポール・スカンラン(Paul Scanlan)氏はNB-IoTの推進について、「いますぐIoTをスタートしたいというニーズを受けてのもの」と説明するが、その背景には、IoT専用としてLPWA(Low Power Wide Area)ネットワークを独自に構築する動きも関係がありそうだ。代表格であるシグフォックス(SigFox)やLoRaアライアンスはホール8にブースを構えていたが、メインから少し離れているにもかかわらず盛況だった。シグフォックスの広報担当は、「グローバルな(IoT向けの)ネットワークは現在の通信事業者だけでは構築できない」と自信を見せた。

ファーウェイの輪番CEO、郭平氏は「5Gを待たずに取り組むべきこと」を提言(写真:GSMA)
自動車業界はモビリティを追求
5Gでは速度ではなく低遅延も重要な要素となる。今年は、低遅延が要求される産業ロボットを遠隔から操作する様子を紹介したエリクソンなど、5Gの重要なユーザーである“モノ”用途のデモが増えたことも印象的だった。
標準化と利用の両方で5Gがこれまでの通信技術と大きく異なるのは、産業界の参加だ。5Gが実現する高速で低遅延のモバイル・ネットワークは、自動車、製造、医療などさまざまな業界がそのメリットを享受すると言われている。会期中、欧州連合(EU)の5Gイニシアティブである5GPPP(5G Public-Private Partnership)は製造、自動車、eヘルス、エネルギー、メディアとエンターテイメントという5業界との協業結果に関するレポートを発表した。EUでデジタル経済・社会担当委員を務めるギュンター・ヘルマン・エッティンガー(Günther H.Oettinger)氏は、技術と経済の両方で自動車業界と共通の認識を持っているとして、協業が順調に進んでいることをアピール。レポートはモビリティ(速度)、データレート、遅延、密度、信頼性、位置情報の精度、カバレッジの7つについて5業界の要件レベルをまとめており、今後これら産業界のニーズをどのように取り込んでいくかが注目される。
欧州ではドイツ政府が推進する「インダストリー4.0」など、通信とITの融合がオートメーションを大きく進化させることが期待されており、5Gはその土台技術と位置付けられている。だが、5Gの商用サービスについては、2018年の冬季平昌オリンピックでプリスタンダードの5Gを開始すると見られる韓国、2020年の夏季東京オリンピックで商用サービスが始まる予定の日本など、韓国、日本、米国などが先行することが見込まれる。エッティンガー氏は4Gに続き5Gでも欧州が出遅れることへの危機感を示し、2020年のUEFA(欧州サッカー連盟)欧州選手権が5Gを披露する格好の場となるのでは、と提案する場面もあった。
産業界の中でも自動車業界はここ数年MWCでの存在感を増している。今年は、初日の基調講演にフォードのCEOマーク・フィールズ(Mark Fields)氏が登場、第3世代の車載インフォテイメントシステム『Ford Sync』を発表した。フィールズ氏は車、接続性、デジタル・サービスの融合を強調し、“自動車”カンパニーから“自動車とモビリティ”カンパニーを目指すと語った。
グーグルが自動運転車の実験を行い、アップルが自動車に参入かと言われるなど、デジタルとインターネットによりこれまでの産業の区分けが壊れつつある。既存の自動車メーカーは、自らの変革なしには新規参入のプレーヤーに駆逐されるという恐れがあるのかもしれない。

5GPPPのプレス発表会では産業界のコラボレーションが発表された。EUのエッティンガー委員(左端)をはじめ、ベンダーや欧州の事業者のトップが集まった

フォードのCEO、マーク・フィールズ氏はモビリティを強調(写真:GSMA)
コネクテッドカーはレースの世界にも
メイン・プログラムの今年のスターは、F1ドライバーのルイス・ハミルトン(Lewis Hamilton)選手だろう。ハミルトン選手は所属するメルセデス AMGペトロナスの執行ディレクター パディ・ロウ(Paddy Lowe)氏、協業するクアルコムの社長デレク・アベール(Derek Aberle)氏とともに2日目の基調講演に登場し、コネクテッドカーや自動運転などについて話した。
ハミルトン選手は自動運転車により自分の仕事がなくなることは当分はないだろうと笑ったが、ICTのメリットは実感しているという。ステージでは、クアルコムがチームに導入したWi-Fiベースの通信システムにより、これまで20分かかっていたという重要なデータ(タイヤの温度など)の取得が瞬時に得られるようになったと喜ぶ。このようなデータの効果的な利用や最適化が進めば「勝敗が分かれるだろう」と予想し、情報武装がカーレースの世界でも進んでいることをうかがわせた。
欧州では2018年より新たに販売する車に通信システムの搭載と緊急通報システム「eCall」への対応が義務付けられることが決定しており、MWCを主催するGSMAは自動運転車は2030年には4,400万台に達すると予想している。クアルコムのアベール氏によると、2015年に販売された車のうち、約3分の2がBluetoothを搭載していたとのこと。「LTE接続ができる車や、Wi-Fiでホットスポット化した車も増える」と述べ、「車はモバイル・プラットフォームになる」と予想した。

基調講演で自動車の未来を語ったクアルコム社長、デレク・アベール氏(左から2番目)とF1レーサーのルイス・ハミルトン氏(左から3番目)(写真:GSMA)
SDN、NFVからネットワーク・スライシングへ
5Gに関連してもうひとつ各社が力を入れて展示していたのが「ネットワーク・スライシング」だ。
NFVによるコア・ネットワークの仮想化の次のステップとして、物理層をスライシングして専用のネットワークを作ったり、大規模なIoT向け、低遅延に特化したものとニーズに合わせたネットワークを構築できる手法として紹介されていた。ネットワーク仮想化の商用化に向け開発に着手したことを発表したNTTドコモ、それにSKテレコムなどの通信事業者やベンダー各社で展示があった。ファーウェイは、ドイツ・テレコムと行った実験を披露した。コントロール・プレーンとユーザー・プレーンの分離とコア・ネットワークのモジュール化によるエンド・ツー・エンドのスライシングとなり、柔軟なネットワーク構築が可能になりつつあると予感させた。
クラウドも盛り上がりを見せてきた。エリクソンはパブリック・クラウド最大手のアマゾン ウェブ サービス(AWS)との提携を発表、通信事業者のITのクラウド化をAWSとともに推進していくと意気込む。ファーウェイはクラウドに特化した「OpenCloud」コーナーをブース内に設け、サーバー、ストレージなどのITインフラ・ハードウェアを持つ強みを生かし、ITとCTの両方でクラウドへの移行を支援するとアピール。OpenStackベースのクラウド基盤『FusionSphere』を中核に、通信事業者のパブリック・クラウド展開を支援する。同社がドイツ・テレコム向けに構築したパブリック・クラウドは3月に提供を開始し、事業者にとって新しい収入源となることが期待される。

通信事業者のクラウド化を支援するファーウェイの「OpenCloud」
免許不要帯のみでネットワーク構築、「MulteFire」が発足
このように、今年は新しい技術の登場というより既存の技術やコンセプトの成熟を思わせたが、免許不要の周波数帯(アンライセンス・バンド)の利用も同様だった。
5GHz帯など免許不要周波数帯を活用したキャパシティ増の手法として、LAA(License Assisted Access)が2015年に大きな注目を集めた。LAAはRelease13で下り技術が入ることが決まっており、続くRelease 14では上り技術にも拡大する。クアルコムのブースでは上りのLAAをeLAA (Enhanced Licensed Assisted Access)として、Wi-Fiの性能に影響を与えていないことを示すデモを見せた。なお、日本では電波干渉を防ぐ目的で「Listen Before Talk(LBT)」が規制で義務付けられており、そのままではLAAを実装できない。Release 13が出た後で総務省が制度の整備に入ることが期待されている。
LAAではLTE、つまり免許が必要な周波数帯がセットになるが、アンライセンス・バンドだけでLTEネットワーク構築を可能にする技術としてMulteFireが2015年末に立ち上がっており、MWC会期中に推進団体が公式に発表された。設立メンバーであるクアルコムとノキア、それにエリクソンなどのブースで展示が見られた。
すべての人にインターネットを――ザッカーバーグ氏の呼びかけに拍手
前述のとおり3年連続で基調講演に登壇したFacebookのザッカーバーグ氏は、TIP(Telecom Infra Project)を発表した。
ザッカーバーグ氏は毎年、基調講演の場でInternet.orgをアピールする。「すべての人がインターネットに接続できるようにすること」をミッションに掲げ、途上国向けに安価にインターネットを提供する取り組みだ。ここで同社は事業者、ネットワーク・インフラ・ベンダーらと組んで、Facebookや地元のサービスなど一部のウェブサイトに無償でアクセスできる『Free Basics』、短期にインターネット・カバレッジを拡大する『Express Wi-Fi』などを展開している。『Free Basics』は直前にインドでネットワーク中立性に反するとして禁止されたが、これについてザッカーバーグ氏は「残念だ。だが国により異なる」として、今後も他国で同サービスの提供を続ける意思を明らかにした。「Internet.orgは発足以来、38か国で展開しており1,900万人がインターネットに接続できるようになった。これは最初のステップとしては、かなり評価できる」と胸を張る。
TIPはInternet.orgの最新の取り組みとなる。同社はすでにOCP(Open Compute Program)として、データセンターの仕様をオープンソースとして公開し、誰もがこの仕様を土台にデータセンターを構築できるようにした。このプログラムにより、Facebookだけでも20億ドル(約2,260億円※)のコスト削減を実現しているという。TIPはこれを通信インフラに拡大するものとなり、「インフラ構築の効率を改善して事業者がコストを下げることができれば、コンシューマーに利益を還元し、安価なデータプランにつながる」と期待を寄せる。
Facebookが会期中発表した年次レポートによると、インターネットにアクセスできる人は2014年の29億人から2015年には32億人に増え、アクセスできない人は43億人から41億人に減った。成果は見られるものの、ザッカーバーグ氏は「国連が掲げる『2020年までにすべての人々がインターネットにアクセスできる』という目標をわれわれは達成できないだろう」と述べる。そして、「4Gは人、5Gはモノ」としてIoTに向けて急ぐ業界に対し、人の接続はまだ達成されていないと釘を刺す。「少し残念に思っている」とザッカーバーグ氏は切り出し、「すでにアクセスできる人にさらに高速な技術を提供するだけでなく、世界のすべての人にインターネットを提供するという任務を果たしてほしい。われわれはそのためにできる支援をInternet.orgで行っていく」と述べると、会場からは大きな拍手が起こった。
MWCの今年のテーマは「Mobile is Everything」。あらゆる人とモノがつながるという世界を、業界は現実にできるのだろうか。

ザッカーバーグ氏は今回もInternet.orgをアピール(写真:GSMA)
※1米ドル=113円換算
末岡 洋子(すえおか ようこ)
ICTを専門とするフリーランス・ライター/ジャーナリスト。ウェブ・メディアの記者を経てフリーとなり、現在は『ITmedia』『ASCII.jp』『マイナビニュース』などで執筆。欧州のICT事情に明るく、モバイルのほかオープンソースやデジタル規制動向などもウォッチしている。