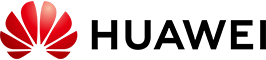ファーウェイ創業者兼CEO任正非 共同通信社によるインタビュー筆記録
任正非:本日はお越しいただきありがとうございます。まず、台風19号で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。また、吉野 彰さんのノーベル化学賞受賞、誠におめでとうございます。38年間におよぶ研究精神に当社も学びたいと思います。中国の研究者も38年間一つのことに一意専心に励めば、中国はもっと良い国になると思います。日本には我々が学ぶべきことが多くあります。本日、インタビューをお受けすることができ嬉しく思います。どのようなことも遠慮なく、ご質問ください。
Q1. お忙しい中、取材をお受けいただきありがとうございます。私のファーウェイとの接点は2012年の上海にさかのぼります。当時、支局長としてファーウェイの上海研究所で開催された記者発表会に参加しました。当時はファーウェイのことをよく知らず、中国にこれほど巨大な民間企業があることを、その時初めて知りました。
幸いにもファーウェイとはその後も交流が続き、当時の米国人の広報部長は完成したばかりのスマートフォンの試作機を嬉しそうに紹介してくれました。その頃から任CEOへのインタビューの希望を伝えてきました。7年が経った今、インタビューが実現したことをとても嬉しく思います。
任正非:上海研究所をご訪問くださり、とても嬉しく思います。ファーウェイがスマートフォン、携帯電話を作り始めたのは偶然の出来事でした。当時、世界各国で3Gの通信機器を販売していたのですが、(通信機器だけがあっても)携帯電話がなければ何もできず、通信機器も売れません。そのため、携帯電話のつくり方を学びはじめたのです。当初の携帯電話の大きさがどれくらいだったかご存知ですか。たった1台の携帯電話が、トヨタ自動車のコースターというマイクロバスが満載になってしまうほどの機器で構成されていました。中国・上海の路上で「携帯電話」を乗せたマイクロバスを走らせながら基地局の性能を検証していました。それが少しずつ今のサイズまで小型化されました。十数年がかりでようやくここまできました。携帯電話の開発初期は成功よりも失敗の方が多く、今に至るまでに多くの紆余曲折がありました。今ようやく成功と言えるようになってきましたが、まだまだこれからです。今後も努力を続けていきます。
ファーウェイの日本研究所は日本企業の皆様とスマートフォンの開発において非常に良好な協力関係を築けています。日本の皆様は職人気質で製品の小型化、精緻化に大変長けていらっしゃいます。そのため、当社は日本に大規模に投資し、日本企業との協力をさらに強化しています。
Q2.米中貿易戦争の解決の糸口が見えないなか、中国と米国が新たな冷戦・新冷戦に入っているのではないかという見方があります。任CEOはどうお考えですか。中国と米国は新冷戦に入った、あるいは今後、新冷戦に突入すると思いますか。
任正非:新冷戦には入らないと思います。米国は自国の閉鎖を進めていますが、一方で中国は一歩ずつ開放を進めています。米国が一つ閉じれば、中国は一つ開けるような状況です。冷戦は双方が閉鎖的にならないと起きず、この状況では新冷戦は生じないと思います。米国には中国市場が必要であり、その一部を失えば経済にも影響を与えます。
例えば、中国の自動車保有台数は約4億台であり、平均10年で買い換えると仮定した場合、自動車の年間需要は4,000〜5,000万台になります。中国は昨年、自動車産業の開放に向けて5か年計画を発表し、外国資本による全額出資が認められるようになったほか、技術移転も求められないことになりました。5年間で関税も軽減され、最終的には非常に低い水準まで下げられる計画です。
中国ではヨーロッパ車は高級車、日本車は高品質と見ており、非常に人気があります。一方、米国の自動車はどうかというと、車体が大きく、燃費も悪いため、あまり受け入れられていません。だからこそ、米国は中国の人々が米国の自動車を購入するよう積極的に努力すべきですが、貿易戦争の末に米国車には25%の関税が課されることとなりました。関税なしでも米国車は日本車と勝負できないのに、関税25%とあっては前途はさらに多難でしょう。数年後にこのことに気づいて政策を見直しても、中国市場はその頃すでにヨーロッパ車と日本車に席巻されているでしょう。このように、中国市場は米国にとってはなくてはならないものです。米国はグローバリゼーションから撤退することはもはや不可能なのです。
最近は中国の金融市場も大きく開放されました。中国がオープンな姿勢を維持する限り、世界を2つの陣営に分断することはできないでしょう。現在、両国の間にはいくつかの貿易紛争がありますが、交渉と調整によって対処されるべきです。一方で、中国と日本はうまく対処しています。ここ数年、中国と日本の間にも多少の摩擦はありましたが、日本政府は一貫して政治と経済と切り離してきました。政治上は中国と日本の間で摩擦が起きても、経済は盛り上がっています。来年の習近平国家主席の来日に向けて、日中関係は新たな高みに引き上げられ、政治的に安定が増していけば、経済における協力関係もいっそう活発になるでしょう。
中国と日本の間には非常に強い補完関係があります。中国には一定のシステム統合力があり、日本には優れた素材・精密技術があります。これらを組み合わせれば、非常に優れたモノづくりができるはずです。私は、中国、日本、韓国による自由貿易圏の形成をかねてから希望しています。ともに工業国家である日中韓は互いに補完することができ、工業を基礎とした自由貿易圏を形成できるでしょう。それに農業が盛んなASEAN諸国が加わりたいと申し出るかもしれません。ASEAN諸国が農産物を提供し、日中韓から工業製品を買うという風に。こうして日中韓の自由貿易圏とASEAN諸国が結びつきます。また、こうなるとヨーロッパからみても、これほどの規模と人口を有する貿易圏は大変魅力があり、仲間入りしたいと思うかもしれません。日中韓の工業とASEANの農業、さらにEUの貿易圏が揃うと、不足するのはエネルギーです。中東や中央アジアの国々は、これら経済規模を見て、石油と天然ガスを供給すると言うかもしれません。そうすればユーラシア大経済圏が出来上がります。この経済圏があれば、どんな経済衰退の危機をも乗り越えることができるのではないでしょうか。
ここで最も重要なのは中国と日本の関係です。日中間の問題が解消され、両国が結束すれば、日中両国が紛争解決の中心的な役割を果たす可能性があります。来年、習近平国家主席が訪日する際、安倍首相との対話を通じて前向きな素晴らしい成果が得られることを期待しています。
Q3. 現在の中国と米国の関係を5G等を巡る技術覇権、ハイテク覇権争いだという見方があります。IT分野で最も進んだ中国企業はファーウェイです。この覇権争いをしているという見方について、どのようにお考えですか。
任正非:私は技術覇権争いに反対です。グローバル化はお互いに依存して成り立っており、1社だけでモノづくりをしていては確実に技術革新が遅れることになります。熱力学に「エントロピー」と呼ばれる法則があり、「エントロピー」は最終的にバランスが取れないと消滅します。何から何まで自力で作るのではなく、世界で分業して各社が作った最高の部品を組み合わせることで最高のモノづくりが可能となります。何もかも自分でまかなって良質なものが作れるとは思えません。私たちは今、米国からの供給が打ち切られるという危機を乗り超えるために、独自の部品を使用して何とか生き伸びることができると考えていますが、3~5年を経た後も当社がリードを保ち続けてられるかは分かりません。むしろ、リードを維持するためには、さらにグローバル化と相互依存を進めて行く必要があります。 日本、米国、欧州にはそれぞれの強みがあり、中国も努力しています。皆で力を合わせて初めて世界最高のモノを作ることができます。したがって、世界は今後も揺らぐことなく、グローバル化の道を歩まなければなりません。
米国の「エンティティーリスト」により、ファーウェイの存続が脅かされるという懸念はありません。しかし、3〜5年経っても先進的な企業でいられるかどうかには懸念があります。この意味で、私たちはグローバル化・相互依存を進めつつ、38年間もの間、たゆまずに一つのことを探究しつづけた吉野 彰さんのように、中国の科学者たちが企業の躍進を後押しするような先進的な研究成果を上げられるよう願っています。米国が非常に優れているのは、世界中から才能を集め、高度な知識、高度なシステム、厳格な知的財産権保護のもとで、連綿と革新を続けてきたからです。
そのような何十年、ひいては何百年もの革新の蓄積によってもたらされた土壌はきわめて肥沃です。米国が数年後には私たちよりも優れた通信機器を作れるのかと問われれば、私は可能だと信じています。ファーウェイが今回の危機を乗り越えた後も成長を続けるという保証はどこにもありません。だからこそ、今後もグローバル化の道を歩み、閉鎖主義を排していきます。
Q4. 米国はエンティティーリストを継続することで、中国経済との切り離し(デカップリング)を図ろうとしているという見方があります。中国政府もデカップリングについて懸念を表明しています。米中経済のデカップリングは今後も続くと思いますか。
任正非:中米経済の分断はないと思います。やはり、お互いに頼りあうべきでしょう。エンティティーリストが撤回されなかったとしても、封じ込められるのはファーウェイだけです。他の大多数の中国企業は米国企業からモノを買うことができます。ファーウェイには世界のグローバリ化の進路を変えるほどの力はありません。制裁を受けずにグローバル化の道を推し進めている企業は他にもたくさんあります。ファーウェイは経済成長の過程で生まれたコメ粒程度の存在です。社会に与える影響はそれほど大きくありません。ファーウェイに同情して、米国と断絶しないでほしいと切に願っています。攻撃されているのはあくまで我々であり、他の企業は我々のことなど気にせず、この機に乗じて大いに成長すれば良いと思います。
Q4-1. 米国が中国経済との切り離しを進めていけば、世界には2つの経済圏が出来るのではないかという見方があります。任CEOの話では、それは絶対に起こらないということですか。
任正非:起こらないと思います。閉鎖主義は後退を招き、開放主義が進歩を呼ぶことは歴史が証明しています。少数の政治家が分断を望んでいますが、多くの企業はそれを望んでいません。誰もがより多くの飛行機を売り、より多くの車を売り、より多くの電子部品を売りたいと思っています。企業の目的は売上を増やすことであり、減らすことではありません。誰かがそれを買いたい、売りたいと思っている限り、分断はないでしょう。
Q5. 日本の高度成長期には、米国に追いつけ追い越せが日本の合言葉になっていました。任CEOがファーウェイを発展させていく上で、米国に追いつけ追い越せという意識はありましたか。
任正非:ある分野で米国の特定の企業を超えることはできるかもしれませんが、米国を超えることは不可能でしょう。米国はかくも強大であり、豊富な技術資源を有しています。当社はある分野でのみブレークスルーを達成するくらいです。
Q6. 世界が今後、5G、6Gへと移行していくと、世界、中国、ファーウェイはどのように変化し、ファーウェイはどのような役割を果たしていきますか。
任正非:ファーウェイは5Gの研究開発に早くから大規模な投資を行ってきたため、当面は先行するでしょうが、これは一時的なものです。また、6Gも5Gと同じタイミングで研究を始めています。6Gは高周波数を使用し、帯域幅が非常に広く、カバレッジがとても弱いです。当分は基幹通信に使うのは難しいため、6Gの使用は10年後になるかもしれません。当社の5Gでの先行は日本の貢献を抜きに実現できません。今後も日本から多くの部品を調達する必要があります。
記者:6Gの実用にはあと10年くらいかかるとおっしゃいました。10年後には6Gの実用化が可能ということですか。
任正非:早まる可能性もあります。個人的な控えめな見積もりですが、光ファイバーが非常に発達した日本のようにな国では6Gを多少前倒して使用する可能性があります。6Gをアクセスシステムとしてのみ使用し、移動通信システムとして使用しない場合は、前倒して使用することができます。実のところ、私たちは5Gの広帯域幅を使い切れないのではないかと心配しており、6Gでさらに大きな帯域幅を求めればなおのこと使い切れないのではないかと思っています。やはり5Gを実際に使用してみて、人々の需要を判断する必要があるでしょう。社会の発展と人々のニーズの拡大に伴い、新たな需要が生まれて初めて新しい技術が登場します。誰も使わない技術であれば、簡単に姿を消してしまうかもしれません。
Q7. 5G時代とAIは切り離せないと言われています。6Gになると、さらにAIの利用が高度化すると思います。我々の生活はスマートフォンなどを使用することで便利になりましたが、今後、5G、6G、AIでどのような変化が起こると思いますか?
任正非:人々のライフスタイルの変化は想像を超えるものであり、情報社会の発展のスピードも速いものです。数年前、ついこの間まで、64kbpsでしかデータ通信ができなかったため、記者の方は三日三晩かけても記事データを送れず、大変だったのではないかと思います。今は1秒で完了します。当時、インターネットにアクセスするためにはケーブルを自宅に引き込む必要がありました。スティーブ・ジョブズ氏の発明によりモバイルインターネットが実現し、爆発的に発展しました。発明はそのように大きな影響をもたらします。5GとAIの組み合わせは、間違いなく社会の大きな進歩を促進しますが、どの程度まで進歩するのかは想像できません。
Q7-1. スティーブ・ジョブズが実現したモバイルインターネットに代わる新しい技術革新が起きる可能性があると思いますか。ファーウェイが、新しい技術を作っていくイメージがありますか。
任正非:将来、AIがもたらす影響はジョブズ氏の貢献によるモバイルインターネットよりも大きいと思いますが、それをファーウェイが創り出せるかどうかはわかりません。
Q7-2. 世界が発展する上で、5G、6Gには大きな期待があるとおっしゃいました。今後、ファーウェイはどのようにビジネスを進めていきますか。5Gをしっかり普及させること、そして6Gに繋げていくというイメージですか。
任正非:ファーウェイはやはり、大容量データの伝送、分散処理、ストレージなどに注力します。膨大なデータが発生するのであれば、伝送や分散処理が必ず必要になります。
Q8. ファーウェイは、これからの技術を牽引していく大きな推進力を持つと世界がその実力を認めています。そのために米国はファーウェイを標的、ファーウェイの技術力、影響力、競争力を米国が削ごうとしていると言われています。そしてそれは、中国の台頭、国力の増強を抑えるためと言われています。任CEOはどのようにお考えですか。
任正非:米国は抑えつけるというよりは、逆に私たちを助けてくれているといえます。現在、従業員は生き残るために必死に努力をし、当社の売上高は第1四半期から第3四半期にかけて24.4%増となりました。抑圧しても一人ひとりの努力まで抑圧されるものではありません。
Q9. 米中両政府は 4日前、中国の米国の農産物購入拡大などを理由に、10月15日に実施予定だった対中国関税の引き上げ延期と貿易協議について部分合意しました。しかし、ファーウェイに対する禁輸問題に関しては進展がありませんでした。今回の部分合意に関してはどのように考えますか。
任正非:ファーウェイのためにこの禁輸措置を解除しようと働きかける人は誰もいないと思います。米議会でこの件を持ち出す議員がいればきっと袋叩きに遭うでしょう。米国内部では、ファーウェイへの攻撃という面で比較的統一されています。私たちも長期間、エンティティーリストが取消されないことを前提に準備をしています。
Q10. 田涛氏が書いた書籍『次に倒れるのはファーウェイか(邦題:最強の非公開企業 ファーウェイ:冬は必ずやってくる)』を読みました。この本の中で任CEOは2003年に、「欧米企業との衝突は避けられない。だから準備をしておこう」と述べています。今起きている衝突は、任CEOが予測したことのひとつですか。2003年から現在までの15年間、そのような準備をしてきたのでしょうか。
任正非:現在起きている衝突は、過去に想像していたよりもはるかに深刻です。米国には自身も参加する「通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント」があり、これにより非軍事の汎用品も管理し、米国の技術は軍事に使用されないよう規制されています。
私たちは民間企業ですが、将来、万が一米国がその適用範囲を拡大し、部品を調達できなくなることを想定して自分たちで専用部品を作ってきました。しかし、米国の攻撃がここまで激しく深刻とは思っても見ませんでした。米国のこのような打撃を受ければ私たちも当然、非常に苦しく感じます。
Q11. 米国におけるファーウェイに対する行動とエンティティーリストについては統一された意見の流れだと仰いました。なぜ、米国でこうした統一した意見が形作られていったと考えますか。
任正非:政治家の意見は一致していると思いますが、企業の意見も一致しているという意味ではありません。
Q11-1. 米国は民主党と共和党の二大政党制をとっています。しかし、両党の政治家の意見が一致している一番大きな理由は何だと思いますか。
任正非:わかりません。日本は1970~80年代の高度成長期に、世界中の企業を買収するほど勢いがついている時に米国から圧力を受けました。ソ連の軍事力が強大になりすぎだとして、米国は今度はソ連を標的にし、結果としてソ連の16か国への解体へとつながりました。
米国は今、中国を当時の日本やソ連のように見なし、中国の発展をスピードダウンさせるために叩いているのかもしれません。ただ、中国が発展すれば大枚をはたいて米国の飛行機や車、食料など、多様なモノを買うことになるとは思い至らないようです。中国経済が本当に低迷したら米国の経済だって落ち込むでしょう。
Q12. エンティティーリストは長期化するとの見通しを述べられました。一方で5Gを着実に進め、6Gの10年以内の実用化を目指していくとのことです。エンティティーリストが長期化する場合でも、5G、6Gの計画、展開にマイナスの影響を受けることはないと思いますか。その影響を避けるための方法はお考えですか。
任正非:基礎研究や理論研究にさらに力を入れ、他国から得られない、買うことのできない新しい理論や技術を手に入れることによって世界に追いついていくつもりです。
Q12-1. 米国からファーウェイに対する輸出が禁止されても、成長し続けることが可能ということでしょうか。
任正非:ヨーロッパや日本など多くの国から調達できます。
Q12-2. 米国の大学や研究機関が、ファーウェイとの研究協力を控えるという状況が影響を与えるのではないでしょうか。
任正非:世界に大学はたくさんあり、米国以外にも良い大学はあります。
Q12-3. 半導体やOS、グーグル、クアルコムのチップなどの米国製技術や製品が無くても5Gは、展開できるということですか。
任正非:はい、そうです。
Q12-4.米国の製品が無くとも5Gを展開できるということが、米国と中国の経済の切り離しとなる可能性があると思います。米国が意図したデカップリングではなく、結果的に、米国にしかない技術、中国にしかない技術が生まれていくのではないかという見方もあります。この点について、どのように考えますか。
任正非:分断は起きないと思います。クアルコムとファーウェイのチップセットに互換性がなければ、1人のユーザーは常に2台のスマートフォンを持ち歩く必要が出てきます。以前はファイルをダウンロードするのは非常に時間がかかりましたが、今は1秒で完了します。基準が2つも3つもあると世界の進歩を遅らせます。政治家とは違い一般の人々はそのような道を選びません。
Q13. 今朝、ドイツ政府が5Gの構築からファーウェイを排除しない方針を示したことへの受けとめを教えてください。一方、日本は昨年12月の早い段階で何の検証もせずに、ファーウェイを事実上排除する方針を決めました。この点について、改めてお聞かせください。
任正非:まず、EUとドイツが事実に基づく方法で、全ての通信事業者にさらに高い安全基準を要求し、5G構築に際し全ての事業者にチャンスを与えたことを歓迎します。ヨーロッパの「データ主権」という考えには大賛成です。かつて、鉱産物や農産品などが富の象徴であった時はどれだけ土地を所有しているかが重要な要素でした。いわゆる「地政学」が絡んでいました。しかし情報社会になると、データには国境がなく世界中どこでも移動できます。「データ主権」という主張を支持した場合、情報産業を基盤に国家の主権を築くことになります。ドイツやヨーロッパのこうした取り組みを大いに支持します。具体的にはある企業にまず不正を行わないことを約束させ、その後、不正を働いたかどうかを検証する仕組みです。不正がなければ良い企業だと判定できます。主観的ではなく、あくまでも事実に基づいて判断する必要があります。ドイツのこのやり方は強く支持できるものです。
日本政府については理解できます。お客様がどのような方法でどのような商品を選ぶのかは自由です。エルメスだからといって、皆が必ず買うわけではありません。
Q14. ファーウェイのスマートフォンは日本で非常に人気です。しかし今後、Google Mobile Servicesが搭載できないタイプが売られたら、日本の消費者はそれでもファーウェイのスマートフォンを買う、とはなかなかならないと思います。これへの対策はありますか。
任正非:海外のユーザーがしばらくの間はファーウェイのスマートフォンの購入を控えたいという気持ちは理解できます。当社としては何とかこの状況を打開できるよう努力しなければならないと考えています。
Q14-1. 努力するというのは独自OSを開発し、独自のエコシステムを進化させていくということですか。
任正非:今、実現できるかどうかは断言できませんが、努力はしていきます。
Q14-2. 5G、6Gについて、通信機器の開発にあわせてスマートフォンも5G、6Gに対応したものを同時に開発していくのでしょうか。
任正非:はい、そうです。
Q14-3. 今の端末はスマートフォン、タブレット、パソコンなどの形ですが、こうした点も変わっていくと考えていますか。
任正非:そうなるでしょう。将来バラエティ豊かな端末が現れると思います。例えばソフトウェアというのは私達が触れるものではありませんが、デバイスを通してそのソフトウェアを使用した体験がどのようなものかがわかります。端末の種類は、今後どんどん多様化して様々な用途のものが出てくると思います。
Q14-4. 90代後半の初回の北京勤務の時に、当時テレビ局の関係者が理論的にはスマートフォンで動画をとり、それをスマートフォンで送れるようになると言っていた時、皆はそんなことがあるわけないじゃないかと笑っていました。それが十年も経たないうちに実現されました。これは大きな驚きでした。
任正非:中国国慶節の祝賀パレートの様子を記録したDVDがありますので、ぜひご覧になってみてください。ファーウェイの5G機器を使って、数万人によるパフォーマンスがテレビで生中継されました。皆さんはメディアの方ですから詳しいと思いますが、従来の放送技術ではこのようなスペクタクルでかつ高画質な映像を中継することは不可能です。大変クリアな数万人のパフォーマンス映像が中断されることなく、スムーズに中継されています。テレビ放送に5Gが活用されたことがこれでよくわかると思います。閲兵式の中継中、テレビ局のカメラマンはリュックサックを背負い、その中に小型基地局のようなものを入れていました。カメラで撮影した映像をリュックサックにある小さな基地局経由で中央テレビ局の編集スタジオに転送しました。5G技術があったからこそ、このような高画質の映像を伝送できることがメディアの方にはよくご理解いただけるではないでしょうか。
数万人による大規模な祝賀パレート、早い動きで有名なマスゲームや行進などの模様が生中継されましたが、中継をサポートした通信機器は全てファーウェイの5G機器でした。パフォーマンスは人々に喜んでもらうために演出されており、政治的なものではありません。
Q15. 米国政府は、ファーウェイの通信機器が情報を盗むのに使われている、安全保障上のリスクがあるとして禁輸措置を取っています。私たちも、どのような証拠があるのか実際に見たこともないのですが。任CEO自身は米国から直接、こういう証拠があると提示されたことはあるのででしょうか。
任正非:当社はここ数十年、世界の多くの国から厳しい監視の目を向けられ、疑われてきました。当社を標的にしている諜報機関も数多くあります。問題があればとっくに見つかっているはずです。当社のITシステムのファイアウォールは米国製品を使っていますが、米国などの国家からの攻撃を防ぐことを目的にしておらず、当社の技術を狙った不正競争を働く一部の競合企業だけを対象にしています。つまり、米国は当社のことを何から何まで把握しているのではないでしょうか。それでも未だに我々にはセキュリティ問題があるという証拠はただひとつも示されていません。
Q15-1. 米国やEUには、中国政府が通信データにアクセスという法的な裏付けがあることを懸念する声があります。中国の社会の仕組みへの疑念がファーウェイに対する信頼度に密接に結びついていると思うのですが、これについてどのようにお考えでしょうか。
任正非:当社はビジネスのみを行う正真正銘の商業組織です。お客様へ責任をしっかりと果たしていかなければなりません。これは私達の義務です。不正行為は絶対にあり得ません。
Q16.任CEOは10月25日に75歳の誕生日を迎えますが、後継者について常に考えていることがあるかと思います。まず、ファーウェイが10年後、20年後、世界をリードする企業であり続ける上で後継者についてどういうものを期待するのか、次に後継者は決めていらっしゃるのかの2つについてお聞かせください。
任正非:当社の後継者についてはすでに制度化されており、何の問題もありません。後継者は誰か1人を指名するものではなく、制度として継承して行く仕組みになっています。私の株主総会でのスピーチ資料を皆さんに後ほどお送りしますが、それには後継者に関して明記しています。私には単独で何かを決める権限はなく、拒否権を持っているだけです。この拒否権でさえ一度も行使されることのないまま昨年末で失効するはずでした。しかし、何かの突発事件が発生した場合に、仮に従業員(注:従業員株主)による熟考を欠いた投票で会社が軌道から大きく逸脱するような事態になることを憂慮しています。そのために拒否権の失効を一旦保留にしました。拒否権を持っていると言っても私の一存で決定事項を拒否できるわけではありません。また今後、この拒否権が私の家族に継承されるようなこともありません。現場から退いた取締役メンバー、監視委員会メンバーまたは上層部のリーダーから7人を選出し、この7人から構成されるチームに引き継がれることになっています。この精鋭チームがいれば突発事件で会社が崩壊するようなことも防げるでしょう。
Q17. ご家族のお話が出ましたが、カナダで拘束されている娘の孟晚舟さんについて、何か新しい動きは出ていますでしょうか。
任正非:司法プロセスに従ってひとつずつ解決されるのを待っているだけです。
Q18. 中国政府は「一帯一路」を強力に推進してますが、ファーウェイとして、この「一帯一路」になんらかの形で協力したり、参加していますか。
任正非:ファーウェイは参加していません。「一帯一路」はインフラ整備を中心に進められていますが、ファーウェイが作っている製品の多くは電子機器です。そのため、「一帯一路」プロジェクトに関わっていません。
Q19. ファーウェイのグローバルでの従業員数は18万8千人と聞いています。米中貿易戦争の影響から、従業員数が減少するなどの影響は受けていますか。
任正非:現在、従業員数は19万4千人になっています。多様な課題を抱える当社を元通りに戻すには、多くの優秀な人材が必要です。そのため新たに数千人を採用しました。
Q19-1. 世界規模で採用しているということですか。
任正非:世界各国で採用を行っています。
Q19-2. 採用に関して、重点を置いている国はありますか。インドやロシアなど理系が強い国に重点を置いていますか。
任正非:採用に関しては特に制約条件を設けていません。ただ米国人の採用は慎重に行っています。米国政府からファーウェイと関わることを禁止されていますから。米国と関係が発生すると、同国から介入される可能性があります。そのため米国の優秀な人材の採用は控えるしかなく、これは当社にとっては大きな損失です。しかし、その他の国や地域での採用はとくに制約はありません。
Q19-3. 米国では、優秀な中国人の研究者がシリコンバレーや大学や研究機関にたくさんいます。そのような米国内の優秀な中国人が圧力を受けているという実態もあります。そのような圧力により、米国にいた中国人研究者が中国本土に戻り、ファーウェイの門をたたくということは起きていませんか。
任正非:中国国籍の留学生なら問題ありませんが、米国の市民権や永住権(グリーンカード)を持つ中国人の採用は難しいです。
Q20. 現在、任CEOが最も欲しいものは何ですか。
任正非:信頼です。世界のより多くの皆さんから信頼していただきたいと願っています。私がメディアの取材を頻繁に受けるのもメディアを通して私達のことを世界によく知っていただきたいという思いがあるからです。私たちはもうベールに覆われるような存在ではありません。最初からベールなどなかったのですが、皆さんがファーウェイについて書いてくださっている間に、ファーウェイのイメージが勝手に作られ、ベールを被せられていただけです。
Q21. 今回は日本のメディアとして初めて単独インタビューの場を設けていただき、嬉しく思っています。忌憚なくお話いただく場を設けていただいたのは、日本に対する期待もあるということでしょうか。
任正非:私は一貫して日本に期待を持ち続けています。私の娘は第2外国語に日本語を選択し、フランス語はその次でした。
Q21-1. お忍びで日本に訪れることがよくあると聞きました。本当ですか。
任正非:はい、日本を旅して、色々見て回っています。
Q21-2. 一番お気に入りの場所はどこですか。
任正非:一つだけ選ぶのが難しいぐらい、殆どの場所をまわりました。九州から北海道まで、田舎から都会まで色々な所に行かせていただきました。日本は世界でも指折りのすばらしい観光地です。行き先を決めずに、足の向くままにいけば、愛らしい小さな村に出会えます。食べ物も美味しく、何か月滞在しても飽きません。
Q21-3. 任CEOの旅行以外の趣味は何ですか。
任正非:仕事です。テレビドラマも見たりします。
Q21-4. 2020年4月に習近平国家主席が来日します。一緒に来日する予定はありますか。
任正非:日本ならいつでも行きたいですね。
Q21-5. 個人で訪れるときは、安全面での心配はありませんか。
任正非:心配していません。
Q22. ファーウェイは世界170カ国でサービスを提供し、従業員も19万4千人にのぼります。一方で、中国の法律的制約があるとは思いますが、取締役には中国人しかいません。今後、外国人の幹部登用は考えていますか。それを推進することで、諸外国からのファーウェイの企業としての透明性に対する評価と信頼につながるのではないかと思うのですが。
任正非:海外の現地法人には決して少数ではない上級管理職がいます。ファーウェイに在籍する3万人ほどの外国籍社員の中には子会社の取締役会メンバーになっている人も数多くいます。ただ本社の取締役会に入るにはそれなりの資格と実績が必要です。外国人社員も現場で長い下積み時代を経て一段ずつ上がって来なければ、取締会のメンバーになっても飾りだけの役員になってしまいます。取締役会メンバーは皆、生え抜きで自力で上がってきたのです。私が任命したのではなく、彼らが実績を積み、自分の得意分野を作ったからです。外国人社員も同じプロセスを経て一歩ずつトップを目指すしかありません。会社は常に外国人に門戸を開いています。当社のフェローの3分の2は外国人です。
記者:我々が事前に考えていた以上に率直にお答えいただきました。非常に有意義なインタビューになったと思います。本当にありがとうございました。