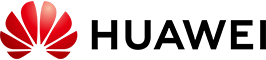ファーウェイ 取締役兼上級副社長 陳 黎芳 日本メディア ラウンドテーブル筆記録
2019年4月15日、ファーウェイ取締役兼上級副社長 陳 黎芳(キャサリン・チェン)は日本の報道関係者とラウンドテーブルを実施し、各社が関心を持っているトピックについて率直に語りました。以下は本ラウンドテーブルの筆記録です。
陳 黎芳:陳 黎芳です。今年は私がファーウェイに勤めて25年目になります。2010年末、ファーウェイでは初めて取締役を従業員代表による選挙で選出しました。私はそれ以来、取締役としてすべての対外的な企業コミュニケーション活動を統括しています。皆様のご来訪を歓迎いたします。こうして交流する機会があることに感謝しております。
1.記者:御社と米政府との問題についてお聞きします。米政府はファーウェイへの圧力を強めており、各国政府にもファーウェイの通信ネットワーク機器を排除するよう求めていますが、このような厳しい局面における御社の渉外・広報戦略を教えてください。
陳:ご質問ありがとうございます。おっしゃるように、米政府は十数年にわたりファーウェイという企業にさまざまな形で圧力をかけてきました。これは余り例のないことだと思いますし、ファーウェイのレピュテーションにも大きな影響を与えています。今後、米政府との問題は主として法的手段により解決していきます。これまでの十数年、私たちもコミュニケーションを通じて彼らの誤解を解き、また、彼らが解決しようとしている課題の解決にも力を尽くしてきましたが、私たちが何をやっても彼らは受け入れることができないようです。現在、すでに司法プロセスに入りましたので、今度は米政府が事実と証拠を提示し、私たちに対する指摘が実際に存在するのかを証明すべき時ではないかと思います。
また司法プロセスは非常に厳密で、とても長い時間がかかります。この過程で我々は法的手段のみに頼る必要はなく、他の手段も用いて自らのレピュテーションを守る必要があります。2019年1月以降、ファーウェイは以前と比べて対外的な企業コミュニケーション活動を大きく強化しました。2月に私自身の名で米紙に掲載したオープンレターにもあるように、その目的は報道機関の皆様にファーウェイに実際に足を運び、見ていただきたいということです。また、当社のテクノロジーに関する記者発表会も定期的に開催していますが、これも皆様に真のファーウェイを、そしてどの企業の技術がより優れているのかを見極めていただきたいという願いがあります。
企業コミュニケーション戦略を実際に遂行するにあたっては、大多数の企業と同じように専門のコンサルティング会社の協力を得て、ともに実行しています。他社と異なるとすれば、ファーウェイ自身がこうした状況を引き起こしたわけではないということです。いずれにしても、すべてがファーウェイに関わることですので、積極的に対応しています。
2.記者:今年に入ってファーウェイの5G製品の採用をめぐる各国の対応が分かれていますが、そのことをどのように見ていますか。態度をまだ表明していない国もありますが、そうした国々にどのようにコミュニケーションをとっているのか、また今後とっていくのかについて教えてください。
陳:今年から本格的に一部の国で5Gの商用化が検討されています。これまでは一部で試験が行われる程度でした。いつ、どのような規模で商用化するのか、また周波数の割り当てに関してもそれぞれの国で事情が異なります。全体的な傾向としては日本、韓国を含むアジアが先行しようとしています。ヨーロッパでも速やかな展開を想定している国がいくつかあります。ただ、それぞれの国で明らかに展開のスピード感は異なります。中国では、いつ正式な免許交付が行われるかはまだ決まっていません。
ファーウェイは5Gの商用契約を今年第1四半期までに30件以上締結し、基地局の累計出荷数も5万8,000局と6万近くに上りました。これは業界トップにあたります(注:本メディアラウンドテーブルの翌日に開幕したファーウェイアナリストサミット2019では2019年3月末現在の5G商用契約数が40件に、基地局出荷数が7万5,000局に達したことを発表しました)。5Gは今年スタートしたばかりですが、今後数年間は5G構築のカギとなる時期です。5Gの市場規模は非常に大きく、競争そのものはファーウェイの主要な関心事ではありません。技術が優れているから競争に関心がない、ということではありません。現在、多くのメディアがファーウェイの5G技術が優れていると報道してくださっています。例えば、特許保有数が最多であるとか、最も早くから投資を始めたとか、5Gの研究開発に携わる技術者が5,000人以上に上るなどです。しかし、より重要なのは5Gを活かしていかにビジネス価値を創出し、また非都市部における通信カバレッジ確保という課題を解決し、5Gエコシステムを形成するのか、ということです。ファーウェイはこうした点により一層注力し、5G市場の活力を高めていきたいと考えています。
もちろん、自社の5G基地局については強く自信を持っています。私たちの5G製品は多くの市場のお客様に気に入っていただけるでしょう。ご覧いただくとより実感できるのですが、ファーウェイの5G基地局は体積では4G対応の従来製品の半分しかありませんが、キャパシティは60倍です。基地局の体積が小さくなることは非常に大きなメリットがあります。重量が30キロ以下、およそ20キロ強となることで、基地局を1人で容易に設置できるようになります。これはファーウェイの5G技術が優れていることを示すよい一例だと思いますし、強く自信を持っています。ファーウェイの5G製品を選択するお客様がいらっしゃる限り、我々はベストな5Gネットワーク構築に向けて協力を惜しみません。これこそが私たちの考え方と戦略です。
3.記者:5Gの契約数が30件以上とのことですが、どの国が多いでしょうか。
陳:ご質問の視点で比較をしたことがありませんが、5Gの導入、展開は始まったばかりです。今後、5G商用サービスについては私たちのお客様から公表されます。ファーウェイは機器ベンダーであり、ネットワークは通信事業者が保有するものですから、正式な発表は通信事業者から行われます。
4.記者:それほど自信がある製品や技術が米国との問題で影響を受けたり逆風を受けたりということは実際に起きているのでしょうか。
陳:影響の有無、そしてその影響の良し悪しを語るのは実際にはとても難しいことです。5Gは第5世代の移動体通信ということですから、これまでの技術よりも先進的で、より安全になるということは誰もがおわかりかと思います。ただ、現在は米国がこれほどまでに5Gを重視し、トランプ大統領も数日に一度はコメントするような状況です。ポジティブな面としては米大統領の影響力はとても大きく、より多くの企業が5Gへの投資を希望し、アプリケーションとエコシステムを積極的に推進させることになるかと思います。これは私たちの業界にとっても良いことです。また、もう1つ良い点は、ファーウェイはこれまで一般の消費者に広く知られていたわけではありませんが、米国の政治家がしばしば当社のことを――批判も含めて――話すようになり、多くの人々に知っていただきました。それだけではなく、「ファーウェイの技術が米国を追い越すことになってはならない」とも話していらっしゃいます。つまり、ファーウェイの技術が彼らよりも優れていることを認めているのです。そうすると多くの人が、米国よりも技術が優れているなんてどのような会社なのだろう?と考えます。もちろん、これにはネガティブな面もありますが、客観的にポジティブな面も存在しており、私たちが思ってもいなかったような宣伝をしてくれたということになります。
5.記者:日本でも先日、5G向けの周波数の割り当てがあり、ファーウェイの通信ネットワーク機器等は使わないことが暗黙の了解になっていると聞いています。このことに対する受け止めと、日本市場でファーウェイの機器が使われないということが、御社にどのような影響を与えるのかを教ください。
陳:まず、私は日本政府が5Gでファーウェイを選定しないと表明したという風には聞いておりません。また、日本では先日、周波数の割り当てが行われ、通信事業者が通信機器ベンダーの選定を始められるようになりました。まだ始まりに過ぎず、現在も私たちはお客様とコミュニケーションを継続しています。仮にお客様が決定をされたとしても、それには1回目、2回目、3回目とあり、必ずしもファーウェイを排除するという意味ではないと思います。あくまで選択の問題に過ぎないのです。繰り返しになりますが、これまでのところ、日本政府やお客様がファーウェイの日本市場への参入を否定したという情報は聞いておりません。
6.記者:ファーウェイを排除する一連の動きに同調する形で、これまでにビジネスとして進めていたものが途中でキャンセルされたことはありましたか。
陳:私は日本政府が(ファーウェイを排除する)米政府に追従するという情報がどのように導かれたのか、明確な説明を聞いたことがありません。日本政府の公式見解でもそのような点は見当たりません。ファーウェイは日本市場で引き続き5G対応通信機器やスマートフォンを販売していきたいと考えていますし、日本企業から多くの調達を行う必要もあります。現時点で、ビジネス上の協力関係に影響が出て、止まってしまったという話も聞いたことはありません。
7.記者:ファーウェイが少し前にテキサス州の連邦裁判所で起こした米政府に対する訴訟の現状と今後の手続きについて何か見通しがありましたら教えてください。また、アメリカやイギリスの大学や研究機関でファーウェイとの共同研究を打ち切った、もしくは打ち切るとの報道が出ていますが、研究開発を重視する会社として今後どのような影響が出るのか、また現在も出ているのかについて教えてください。
陳:ご質問ありがとうございます。素晴らしいご質問ですが、この2つの問題へのお答えは少し長くなります。
まず、私たちが米国の2019年度国防権限法(NDAA2019)889条の合憲性を問うて提訴した件ですが、現在は司法プロセスにあり、お伝えできる具体的な情報はまだありません。ただ、当社としてはこの提訴に自信を持っています。法律上、3つの確かな根拠があります。まずはじめに、合衆国憲法は選択的な制限を行う法律の議会立法を認めてはいません。2つ目に、889条はいかなる行政手続き、司法手続きも経ることなく、(すべての米政府機関に対し)ファーウェイの機器・サービスの購入を禁止しました。最後に、米国は三権分立の国であるということに関わります。つまり、米議会は立法することはできますが、同時に法の裁決と施行まですることはできません。米議会は889条でこれらのことを一まとめにしているのです。立法し、かつ、この889条がファーウェイに適用されると直接認定したこと、これも合衆国憲法に反することです。当社の法務チームは法律上十分な根拠があると考えており、最終的な判決にも自信を持っています。
2つ目のご質問は非常に重要です。単純にファーウェイに影響する、しないというレベルの問題ではないと考えます。まず、なぜファーウェイが研究開発を重視し、多くの大学と協力しているのかについてご説明します。私たちは科学技術は人類共通の挑戦であり、財産であると考えています。科学技術研究はオープンであるべきで、人、国、地域で制約をかけるべきではありません。ファーウェイの理想は、技術がすべての人に平等に理解され、そして利用されることです。企業の立場に置き換えれば、都市、農村、あるいは人里離れた土地や一部異なる事情のある人々でも、ネットワーク技術の恩恵を享受できるようにする必要があると考えます。
当社の研究開発投資は確かに大きく、2018年度は約150億米ドルに達しました。さらに今後は毎年200億米ドル前後の規模になると思います。
ファーウェイと大学の協力には大きく分けて2つの形があります。
1つ目は無償の資金援助です。ご存知かもしれませんが、ファーウェイは上場企業ではありません。そのため、財務諸表上の数字が多少変動してもあまり影響ありません。(研究テーマの)より深い探究と開拓につながるのであれば、私たちは喜んで支援します。皆さんもご存じのとおり、この業界では研究や探究が先進的であればあるほど、その道のりは非常に苦しいものです。我慢強さが必要です。多くの研究、探究は数年、数十年経って初めて結果が出ます。このような取り組みに情熱を傾ける科学者は大変素晴らしいと思います。彼らは人類のために研究、探究し、信念をもって多くのつらい仕事も果たしています。ファーウェイはこのような方々を支援したいのです。
2つ目の形は、プロジェクト研究によるものです。これは大学とファーウェイの双方に大きなメリットがあります。ご存知のように、象牙の塔から仕事や生活の場に技術を活かしていく過程にはとても長い時間がかかります。構想から技術へ、技術から製品へ、最後に製品が商業的な価値を持つまでには非常に長い時間がかかるのです。大学と企業とが協力することでこの全体のプロセスを短縮することができます。大学がこうした協力を歓迎する理由はファーウェイが資金を提供するからという以上に、このような協力が大学と教員の研究を前進させるからです。学生のスキル向上にもつながります。大学と企業の協力が喜ばれる理由はこのようなところにあると思います。
ファーウェイが大学と協力し、大学の研究・探究を無償で支援するのは、技術は全人類に活用されるべきだと思うからです。これは灯台のようなもので、研究成果である技術はファーウェイのみならず、すべての企業を照らすべきものです。ご質問への回答になっているかどうかわかりませんが、仮に米政府の影響から協力を望まない大学があると、私たちに影響が出るのかどうか。それは何とも予想できません。
8.記者:米国の圧力で御社を排除する動きが進んだ時、使わないと言った国の企業、御社に部品等を提供しているサプライヤーに対して、取引を減らしたり、取引を辞めるといった対抗措置をとる考えはありますか。また今回のことで、御社の採用面で影響は出ているのでしょう。
また、社員の皆さんのアメリカやカナダへの出張は通常通りに行われているのでしょうか。
最後に、先ほど科学技術は人類が共有するもので開放的でなければならないとおっしゃられたことは私もとても賛同しますが、中国政府自身が外資に対して外国の科学技術を人類で共有して開放的に受け入れているかというと、外資の投資等について一部制限的な部分があると思います。他の国にそうした要請をするのであれば、中国政府に対しても御社のような影響力のある企業が声をあげていくことで間接的に世界的な影響を及ぼせるのではないかと感じるのですが、どのようにお考えでしょうか。
陳:第一に、私たちが直面しているチャレンジと、私たちが業界全体をどのように発展させていくかということは、同じ問題ではありません。米政府は当社に対して圧力をかけていますが、明らかなのは、ファーウェイと米国企業との協業には影響を与えていないということです。実際、私たちのICT業界では、米国企業を含めて1つの企業が単独で製品やサービスの開発・製造を完結することはできませんし、そうする必要もありません。あまりにもコストがかかり、広く消費者に提供することが不可能になってしまいます。米国市場で困難に直面したからといって米国企業と協業しないなどとしても、ひとつも良いことがありません。ファーウェイはこのようなことはしませんし、米国もそうしないと信じます。米政府は、仮に中国や日本、韓国の企業と対立したら、中国や日本の市場ではビジネスをしないのでしょうか。私はそんなことはないと思います。企業がものづくりをするのは、それを誰かに使ってもらいたいという思いがあるためだと思うからです。
次に採用について、私は当社の足元の事実においても、いかなる影響も受けないと思います。 まず当社では、米政府が私たちを不公平に扱うならば、例えば私たちも米国国籍の方々に対して偏見を持って接するということは絶対にありません。第二に、米政府がいわば自分自身の身内に干渉するかは、先ほど申し上げたとおり、私には判断できません。なぜなら、今回の件で、米国は果たしてファーウェイの評判を高めてくれるのか、あるいは経営に打撃を与えるのか、まだわからないからです。今、結果から言えることは、業績は好調だということです。圧力の悪影響は受けていません。2018年度(2018年1~12月)の売上高は約20%成長し、純利益は25%増加しました。2019年第1四半期の売上成長率は30%、利益成長率は35%でした(注:2019年4月22日に発表した2019年度第1四半期業績発表では売上高が前年同期比39%成長となったことを明らかにしました。詳細はこちら)。
9. 記者:米国や日本、オーストラリアからのの求人応募は減っているのでしょうか。
陳:変化したとは感じていません。最も多く採用するのは新卒者です。元々新卒採用が大きな比率を占めています。中途採用者もわずかにいますが、明らかに変わったという感覚はありません。
ファーウェイ・ジャパン広報部:日本法人の内定者は11人で、辞退者なく今年4月を迎えました。
陳:3つ目は、米国出張もさしたる変化はありません。当社は米政府から同国で事業をすることを禁じられ、コンシューマー向け端末ビジネスからも排除されています。出張頻度はビジネスに依存します。ビジネスがあれば、その拡大のため市場に出向く必要があります。この意味では出張は減っています。行く必要がないためです。しかし必要がある場合は当然行きます。例えば、カナダは今年に入って取締役会長など複数の経営幹部が訪問しています。
最後の中国政府についてのご質問ですが、私はこの分野に比較的明るいです。普段から中国以外の国との接点が多く、顧客のほか、政府や報道機関ともやりとりをしています。そのためよくわかるのですが、中国を見ると、常に多くの面で市場競争の需要に応えられていないと実感します。一方で、中国に暮らし、主に中国で働く私のような者がまた実感することがあります。それは中国政府は確かに進歩し、一つの場所に留まることなく変化しているということです。全国人民代表大会では今年、外国企業の中国への投資に関する外商投資法が採択されました。これまで外国企業が強い不満を抱いていたいくつかの条項が改正されていることを私も確認しました。例えば、知的財産権保護の強化や中国での会社設立時における出資規制の変更などです。自動車や金融は遅くとも2022年までに出資規制が撤廃されます。
ファーウェイが何かしらの働きかけをしたかというご質問ですが、もちろんしています。オープンな市場こそ企業に有利と考えるからです。例えば知的財産権の保護を求めています。何年も前にヨーロッパに出張した際には、同地域の企業による中国政府の研究開発プロジェクトや、中国政府が設立した標準化団体への企業の参加を制限すべきか否かといった議論がありましたが、そうした問題はすべて解決されました。 もし今後、日本政府や顧客などから具体的な要望があるようであれば、ぜひ教えてください。私たちは中国国内でも多くの税金を支払っており、一定の影響力を持っています。単に働きかけるだけではなく、公の場に出て広く訴えることもできます。
10.記者:先ほど、2018年度通期の業績が伸びていること、また2019年度第1四半期も伸びているということでしたが、昨年を見ると、コンシューマー向け端末事業がかなり伸びています。米国等からのいやがらせとも見える逆風がありながら、これだけの実績を残すことができた要因について、数字以外の要因、実感などががあれば教えてください。
陳:この結果は圧力があったから達成されたものではありません。過去30年間、お客様に最善を尽くしてきたこと、そして当社の製品技術がお客様のビジネスに価値をもたらすことができたからこそだと思います。お客様はこの30年間でファーウェイを理解し、好感を持ち、私たちの将来性に強い自信を持ってくださるようになりました。これが最も重要な理由だと考えます。いかに外的環境が変化したとしても、私たちは発展し続けたいと考えています。これが最も重要なことです。
こうした業績数値に加えて、具体的な事業活動以外の部分でも変化を感じていることがあります。それは社員に一種本能的な団結が生まれていることです。外部に圧力があると、内部により強い団結が生まれるのです。より良くなろう、そして自らを証明しようという思いが原動力になっていると感じます。私は会社の経営を管理する立場にありますが、皆も指示にすぐに反応し、進んで対応してくれるようになりました。
11.記者:米国の大学との共同研究に関する問題の背景には、研究に協力していた海亀族と呼ばれる人々が中国に戻った後に高報酬で雇われ、技術を盗んで持って帰ってくるという疑いがあるように思います。会社が知的財産権を盗むとか盗まないとかではなく、採用した人材が知的財産権を持ってくる可能性について、御社としてどのような対策をしているのかをお聞きかせください。また、先ほどおっしゃっていたように、中国政府は外商投資法などで進歩している面はありますが、この5~10年、中国国内での情報統制は後退している面もあると思います。特に今、問題になっている国家情報法については国民が国家の情報活動に協力しなければならないという点がネックになり、中国の国としての印象がそのままファーウェイの印象になってしまっている、日本の一般の人たちもそのように誤解をしている部分があると思います。こうした点をどのように乗り越えていくかについて教えてください。
陳:たいへん重要な問題です。まず1つ目のご質問ですが、当社との協力を中止すると発表した大学は限られています。先ほど触れたように、このような資金提供は純粋に大学の研究活動を支援するもので、当社は毎年3億米ドルを無償で提供しています。これは現在も変わっていません。受け入れを辞退するという申し出があればそのご意向に沿うしかありません。無理することはないと思います。
2つ目ですが、当社は方針として、経験者採用における前職での成果を携えての転職は禁止しています。こうしたことで当社事業が何らかの影響を受けることを避けるため、このような背景を持つ人材の採用要件を明文化し、当社方針としています。
米国がこの点を非難するのであれば、まず事実を尊重していただきたいと思います。他社の技術を窃取したり、他社の社員を引き抜くことで得られる小利で成功できる企業はありません。ハイテク企業のみならず、どのような企業であってもです。まったく論理的ではないと思います。技術を盗んで成功したハイテク企業など聞いたこともありません。世界で一流と呼ばれるハイテク企業の成功を支えるものは長年のたゆまぬ努力と継続的な投資でしかあり得ません。仮に当社の対応が甘くなれば社員のモラルが低下し、当社の知的財産権が持ち逃げされるかもしれないという危機感さえ持っています。企業にとってはこうした価値観を従業員と共有することが大切です。
また中国の国家情報法についてのご質問ですが、極めて厳正に対処しなければならない問題です。もし、このような状況に直面した時に、当社がどのように振舞うことができるかをまずお話します。創業者は、「いかなる政府からこのような要求を受けても断じて応じることはない。それを受け入れるなら、会社を畳んだほうがましだ」と宣言しています。さらに当社はドイツ政府やEUに、「No Spy Agreement」に対応する用意があると伝えました。「当社は当社の製品にバックドアをしかけることも、他国の情報を収集することもしない。違反することがあれば犯罪とみなされる」という内容の合意書です。他社はやりたくないかもしれませんが、ファーウェイはこの取り組みを支持します。私たちは皆さんの懸念を理解できます。私自身も米国の「CLOUD法(Clarifying Lawful Overseas Use of Data)」やオーストラリアのアンチ暗号化法「Assistance and Access Bill 2018(援助および傍受法案2018)」を読んだあと、同じような危惧を感じたからです。だからこそ、当社はきちんと態度を示し、行動を取らなければならないと思いました。
先ほど、当社はそのようなことを断じてやらないと公約しているとお伝えしましたが、加えて一層サイバーセキュリティを強化していかなければなりません。これは管理や技術手法で強化を図る必要があるため、技術投資を拡大していきます。すでに昨年末に取り組みを始めており、初期投資として20億米ドルを決定しています。当社のソフトウェアエンジニアリング能力とセキュリティにおける信頼性を大幅に引き上げることが目的です。当社のこのような姿勢、そして技術面での強化に加えて、第三者機関による検証試験、認証も不可欠と考えます。当社はこれまで、イギリスのファーウェイサイバーセキュリティ評価センター、カナダやドイツの検証センターの監視・試験を受けてきました。これらの検証試験はすべて各国政府主導の下で行われており、当社製品はそのすべての試験に合格しています。また、その他の第三者機関の検証・認証も受けており、今後も継続していきます。各社のコミットメントと能力を第三者機関の試験によって実証する必要があります。
やや専門的な話になりますが、当社はネットワークインフラ向け通信機器を主力事業にしている企業です。そのため、当社が提供するのは機器であって、ネットワークおよびユーザーデータは通信事業者が管理しています。ネットワークの安全性を高め、個人情報を保護するには政府や通信事業者、当社のような機器ベンダー、そして利用者のすべてのステークホルダーの努力が求められます。サッカーチームに例えるならば、どんなに優秀な選手でもチーム全員の仕事をすることはできません。フォワードやゴールキーパーなどそれぞれが役割を果たす必要があるのです。
また、すでに報道機関による報道が数多くなされていますが、中国政府も折に触れて本件に関する態度を表明しています。ドイツ・ミュンヘンで開催された安全保障会議では中国・国務院委員の楊潔篪氏が、全国人民代表大会後の記者会見では李克強首相も、「中国には企業にバックドアを要求する法律は存在しない。政府は企業に他国のデータや情報を収集するよう求めることはない」と発言しています。これらの上層部のコメントは中国政府を代表しているはずです。政府はがこれほど明確にし、当社も同じ認識であるため、政府がこれを反故にするようなことはないと信じています。繰り返しになりますが、当社は過去30年間、中国政府からこのようなことを求められた事実は一度もありません。
12.記者:ビジョンについて教えてください。ファーウェイとしてデータを活用して利益を生み出していくことについて、どのように考えていますか。過去30年間、政府から提供を求められたことはないとのことですが、今後提供を求められた場合にどのような対応をしていくのか改めて教えていただけますか。
陳:当社の創業者と上層部の言葉を繰り返すことになりますが、お客様の利益を損なう、いかなる政府からの要求にも応じることはありません。ご質問で当社のビジョンに言及されましたが、10年後、20年後には本格的なインテリジェント社会、すなわち、あらゆるモノがインターネットにつながる世界が到来することは当社のみならず、多くの企業が認識していると思います。そうなればサイバーセキュリティ保証や個人情報保護が社会の重要な基盤になることは間違いないでしょう。この基盤が堅牢でなければ、人々は安心してインテリジェント社会を迎えることはできません。当社の事業の一つである通信機器で言えば、例えば5Gは通信機器を使用するための技術に過ぎません。個人ユーザーのデータは当社が所有するものではありません。当社はデータに触れることもできません。ましてやそれを収益化することはあり得ません。お客様である通信事業者が保有・管理するネットワークなのです。当社はモバイル端末を提供していますが、利用者の皆様の情報は皆様の端末に保存されており、当社に送られることはありません。当社はEUの一般データ保護規則を遵守しています。法人向けICTソリューション事業とクラウド事業でも他社とは少々異なります。お客様の利便性と生産効率を高めるためにデータに触れることもありますが、それを収益化することは絶対ありません。やってはならないことです。それを行っている企業がうんぬんというのではなく、当社はやりません。
13.記者:創業者兼CEOの任さんがハイシリコンの5Gチップセットを米アップルに外販しても良いとおっしゃいました。私の理解ではハイシリコンが中核的なチップセットを外販したことはなかったと思いますが、実際にアップルとの交渉が進んでいるかなど事実関係を教えてください。また、アップル以外にもハイシリコンのチップセットを外販する方針に切り替えたということでよろしいでしょうか。2点目は、米政府との訴訟中ではありますが、IT産業のブロック化が進み、サプライチェーンに影響が出る可能性に備えて、安全な調達先を探したり、シフトするなどの措置は進めていますか。
陳:まず、1つ目のご質問については創業者兼CEOの任正非からアップルに製品を供給するという話はしていません。「アップルに部品を売ることを考えていないか」と質問され、当社はオープンな姿勢をとっていると受け答えただけです。アップルが買うかどうか、買えるかどうかについては一切わかりません。仮にアップルに買おうという意志があったとしても、米政府が許可するかどうかも含めて知る由もありません。そのため、ご質問に答える立場にありません。
2つ目のご質問ですが、米政府との訴訟と当社の事業展開、そして他社との協業、この3つはまったく別のことです。例えば日本の場合、当社が日本でつまずいているとの報道がありますが、当社の日本企業との協業がこれによって影響を受けることはまったくありません。昨年度の日本企業からの部品等の調達は66億米ドルでしたが、今年は80億米ドルに達する見込みです。将来的には年間100億米ドルに上ると予想しています。当社の予想どおりに5G市場が成熟に向かえば、当社の事業成長は今後5年間で現在の規模の倍となるでしょう。そうなれば日本企業との取引もさらに拡大します。アルゴリズムなど数学分野を得意とするファーウェイと部品・部材で連携する日本企業とは相互補完的です。日本企業の得意分野に踏み混むつもりはありませんし、そうしようと思っても追いつけません。これが当社と日本企業の協業スタイルです。日本企業との協業は日本市場だけではなく、グローバル市場に製品やサービスを提供するためのものです。当社は将来を極めて明るく見ています。
14.記者:1つ目のご説明について、ハイシリコンは外販しないという従来の方針が、やはり変わるという風に聞こえますが、いかがでしょうか。
陳:検討していません。初めて本件が報道されたとき、まったく見当がつきませんでした。記者の方が任正非に質問したのもそのせいかと思います。つい数日前のことです。
本日は貴重な時間をありがとうございました。皆様から米国の問題について数多くのご質問をいただきましたので、もう少し補足したいと思います。
創業者兼CEOの任正非がファーウェイを創業した時、わずかな資金と数人の従業員しかおりませんでした。それから従業員が数十人、数百人と増えていき、現在は約9万7,000人の従業員株主を擁する企業に成長しました。これだけの従業員が会社に投資しているため、当社の研究開発費は2018年度で世界第5位の規模に上りました。従業員一人ひとりの出資金で成り立っているのです。当社は世界中の通信環境が整備されること、世界の人々が平等に通信ネットワークを利用できるようになることをビジョンに掲げ努力してきました。30年をかけてそれを実現しつつあることを誇りに思っております。欧米企業が避けてきたことも数多く取り組んできました。例えば自然環境が苛酷な砂漠や極寒地帯、山頂などにも通信機器を設置しました。通信復旧のためであれば危険な被災地にも足を運びました。
2つ目に、米国政府がサイバーセキュリティを完全に政治化していることは間違っていると考えます。これではサイバーセキュリティ問題の解決にはなりません。米国では当社の通信機器は使われておらず、米国でこの数年、発生している悪意あるハッキング事件や開示されているセキュリティホールにも当社は一切関係していません。このような状況で、なぜ当社の通信機器が安全でないと断定できるのでしょうか。
何をもって安全というのか、安全ではないとはどういうことなのか考える必要があります。例えば、日本では福島第一原発事故がありました。当社の社員はこのような時にも通信障害復旧に駆けつけました。被災地の皆様がご家族や友人と一刻も早く連絡できるようにしたいという願いからです。安全とはこういうことではないでしょうか。
4月12日、トランプ米大統領は5Gについてコメントしました。大統領はこれからも当社を追い詰めていくでしょう。しかし「5Gの競争は米国が勝たねばならない競争だ。影響力が大きいこの未来の産業で米国は他国が勝つことを許すわけにはいかない」という大統領の発言には賛同できません。道理にかなっていないのです。他の国や企業にも発明や開発をし、新しい技術を使うこともできるようにするのが筋ではないでしょうか。